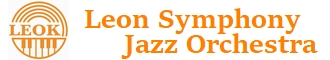スコアを読むって楽しい!音楽のレシピと地図をのぞいてみよう
今日は「オーケストラスコアを読む面白さ」について書いてみます。
私は中学生の頃からスコアを集めて研究していました。
当時、神田神保町に住んでいて、近所に「古賀書店」という音楽専門書店があったんです。ほぼ毎日のように入り浸ってました(笑)。
レコードを聴いて「この音色きれいだな〜」と思ったら、スコアをめくってみる。
すると「えっ、ホルンとチェロの組み合わせでこんな豊かな響きが!?」とか「弦をこんな重ね方すると重厚感が出るのか!チャイコフスキーの秘密みっけ!」とか発見の連続です。
例えば有名な「剣の舞」。ずっと四拍子だと思ってワクワク聴いていたのに、スコアを見てびっくり。「えっ、ここ、まさかの三拍子!?」と声が出ました(笑)。スコア見なかったら一生四拍子だと思っていたでしょう。なぜバッキングは四拍子ふうのままで旋律だけ三拍子で書いたのか、ハチャトリアン先生いたら意図聞いてみたいですね。・・などなど、以来私のなかで「スコアはびっくり箱であり玉手箱」説が確立しています。
そう、スコアってまさに音楽の「秘密のレシピ帳」みたいなもの。
料理でいうと「隠し味にしょうゆを一滴」とか「ここでハーブを振りかけて」みたいな、そんな職人ワザが詰まっているんです。
オーケストラやアンサンブルで演奏している皆さんも、ぜひパート譜だけでなくスコアを広げてみてください。
自分のパートが、ここは「メインディッシュ」なのか「名脇役のスパイス」なのかが見えてきます。
そして、もしかしたら楽譜のあいだに、作曲家がこっそりふりかけてくれた「きらりと光る金の粉」が見えるかもしれませんね。